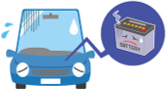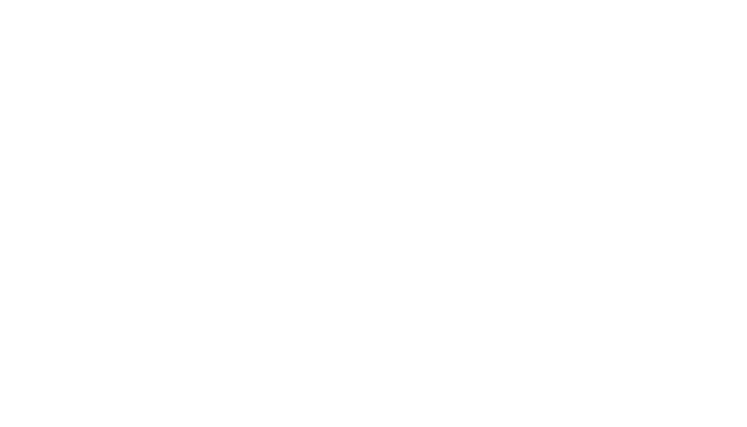 性能向上!”良いバッテリー”って?
性能向上!”良いバッテリー”って?
バッテリー通信
2025年10月
”高性能”ってなに? バッテリーに限らず一般的に商品の良し悪しの判断基準として「壊れにくい」や「性能が高い」などが挙げられます。バッテリーでも各メーカー毎に価格帯にあわせて性能価格比の異なるラインナップを展開しています。 […]
”高性能”ってなに?
バッテリーに限らず一般的に商品の良し悪しの判断基準として「壊れにくい」や「性能が高い」などが挙げられます。バッテリーでも各メーカー毎に価格帯にあわせて性能価格比の異なるラインナップを展開しています。VARTAでもSilver・Blue・Blackと展開しており、容量やCCAだけでなく、バッテリーの性能としてそれぞれ約10~15%の性能差があります。
違いとしては端子の素材や添加物、フレーム強度、バッテリー液の量や二重蓋構造などがあげられます。
しかし多くの輸入バッテリーは日本市場では「輸入車=高級車」のイメージがあるため、輸入車用バッテリーは各メーカーの最高位のラインナップを中心に販売されています。
では”良いバッテリー”とは、昔と比べて「壊れにくい」だけでなく何が変わっているのでしょうか?
バッテリーの”進化”年表
1990年代バッテリーの品番としてドイツ工業規格であるDIN規格(Deutsches Institut für Normung)が用いられていました。DIN規格ではバッテリーのサイズや端子の形状、容量(20h)が定めらめていたため、端子の種類(アンチモンやハイブリッド、Ca-Ca[カルシウム-カルシウム])や“容量が大きい”ことがよいバッテリーとして評価されていました。当時の品番変更では同一サイズのバッテリーの容量が大きくなり、性能があがる場合がほとんどでした。当時の品番は汎用的で今でも56219[L2]や57412[L3]、60038[L5]などが使用されているのはその名残といえます。
1993年のEU統合を機にEN規格が導入され始め、2000年代初頭からDIN規格からEN規格が普及し始めます。EN規格ではCCAも表記されており、また同時期に普及し始めたAGMバッテリーは従来品と比較し、CCAが高かったため“パワフルなバッテリー”として人気が高まります。AGMはL3サイズのものがL4サイズSLIと同じCCAを出すことが可能と言われていました。バッテリーサイズをコンパクトに出来るパワフルバッテリーとして普及が進みました。
2010年代にはEN規格が主流となります。この頃になると容量はバッテリーサイズ毎にL2:60Ah,L3:70Ah,L4:80Ahが一般化しており、元々寒冷地での始動力をあらわす指標だったCCAが、ディーゼル車、とくにコモンレールといわれる高圧燃料を利用したエンジンでは高CCAが必要とされるため、容量よりも“CCAが高い”バッテリーが高評価を受け、品番が変わるごとにCCAが高くなることが多くなりました。
2020年頃になるとEVやHV車が普及し始め、始動用バッテリーは始動用(クランキング)としてではなく、補機系統に使われるため、CCAよりもRCや容量(Ah)が再び重視され初めます。バッテリーの新商品は容量が大きくなり、結果としてCCAも大きくなっている場合もあります。また国産メーカーでもJIS規格からEN規格のバッテリーを搭載するモデルが増え始め、これらの一部のHV車では自動車発進時はモーターが作動するためエンジン始動力としてのCCAはあまり必要なく、回生ブレーキ等によるチャージを受け入れるための充電制御(=充電受入性能が高い)バッテリーが必要となります。
これ以外にもレジャー用途では電装品のバックアップ電源として利用されるため、バッテリー単体での持続時間であるRC(Reserve Capacity)が指標として重視されますし、トラックや産業用バッテリーでは、用途に合わせて「耐振動性」も重視されています。またxEVといわれる電動化がさらに進み、既述の充電受入性能や乗用車用、大型用ともに「マイクロサイクル耐久性」も強く求められており、 EU圏ではこの耐振動性やマイクロサイクル耐久性などを”EN50342-1”や”EN50342-6”というテストで測定し、その結果をバッテリーの品質の基準としています。
令和の新車には高い容量、そして見えない「マイクロサイクル耐久性」や「耐振動性」など見えない性能値が求められています。見えない性能を見える化しているメーカーの商品はメーカーが自信を持っている商品であり、エンドユーザー様が購入時に選ぶ新たな判断基準になるかもしれません。