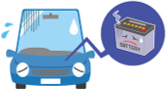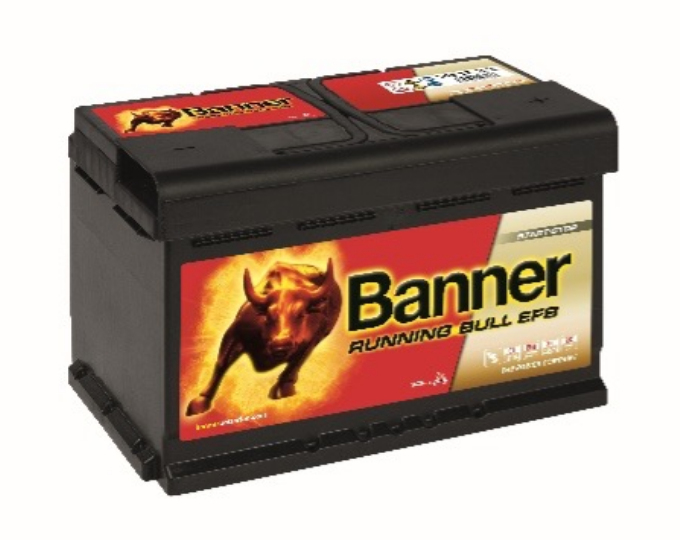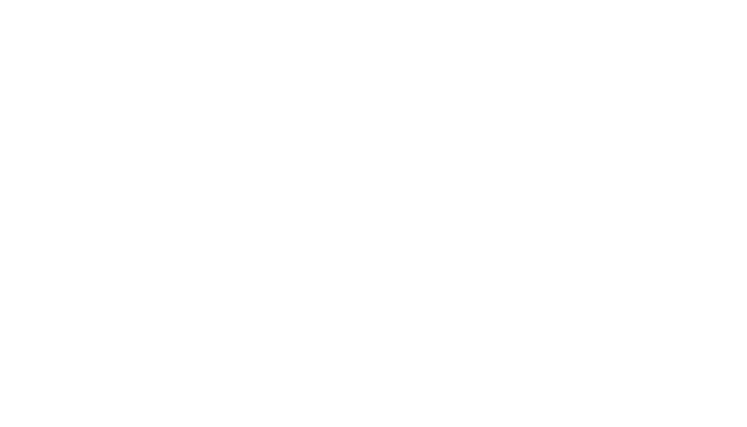 JAFの年間出動要請案件No1”バッテリー上がり”!
JAFの年間出動要請案件No1”バッテリー上がり”!
バッテリー通信
2025年08月
バッテリー上がりの要因とは バッテリーを取り扱う上で、切り離せない”バッテリー上がり”。JAFの出動要請の要因No1はほぼ毎年”バッテリー上がり”です。その数は年間 220万に及ぶ出動のうち約35%を占めています。 よく […]
バッテリー上がりの要因とは
バッテリーを取り扱う上で、切り離せない”バッテリー上がり”。JAFの出動要請の要因No1はほぼ毎年”バッテリー上がり”です。その数は年間 220万に及ぶ出動のうち約35%を占めています。
よくドライバーが勘違いされますがバッテリー上がり=バッテリー不良ではありません。むしろバッテリー以外にその要因があるケースがほとんどです。
まずは代表的なバッテリー上がりの原因を以下に挙げてみました。
- 過放電・・・室内灯や前照灯等の消し忘れ、電装品の電力消費過多や取付不良
- 過負担・・・社外ナビやオーディオなど高負荷な電装品によるバッテリーの容量不足
- 充電不足・・・オルタネーター(発電装置)の故障や駆動ベルトの緩み
- バッテリーの劣化
- バッテリー端子の腐食や緩み
1.2.に関して最近では自動車の性能の向上によって消し忘れ防止のアラームやヘッドライト等の”AUTO”機能の普及、また以前は多かった後付け部品のトラブルもUSBが一般化しこちらしか使わない方も増えています。昨今では車載コンピューターが自動車を統括的に制御するようになり、オルタネーターなどの故障や負荷のかかる電装品(後付け含む)などもモニタリングしており、「バッテリーが弱くなってエンジンのかかりが悪くなる」ことはほとんどありません。ドライバー様の感覚では認知できませんので、バッテリーは”早めの交換”が大切です。猛暑の続く夏だけでなく気温の下がる冬もバッテリーの化学反応が鈍くなり、始動電力が不足しやすくなります。
意外に見落とされやすいのが5.のバッテリー端子。端子に付着したバッテリーの硫酸塩やボディ側の接触不良などが起因しバッテリーが充分に充電されないケースがあります。ヤスリなどで磨くことで解消される場合もあります。
バッテリーに異常がでたら…
バッテリートラブルが起きた際には、まずは基本的にバッテリーの電圧やクランキング電圧の測定やオルタネーターの出力確認を行うことになります。また暗電流の測定も故障診断の重要な整備作業です。すぐにバッテリーを取り外してしまわれる業者様がたまにいらっしゃいますが、上記の内容のようにバッテリー自体の不良はあくまで一要因でしかありませんので、車体状態のチェックが優先されます。
またバッテリー上がりと混同されやすい症状として”盗難防止セキュリティの誤作動”があります。バッテリーが上がった状態でも盗難防止は作動し、イグニッションへの電源供給をカットしていますので、ジャンプスタートし電源が回復しても盗難防止をオフにしないとエンジンはかかりません。
バッテリー種類による違い(AGMとEFB)
AGMバッテリーとEFBバッテリーはどちらもアイドリングストップ対応のバッテリーですが、充電・放電の性能にそれぞれ違いがあります。そのため車載コンピューターの設定と異なる種類のバッテリーを搭載した場合、過充電や充電不足によるバッテリーあがりの要因になります。またAGMは内部抵抗が低く、電圧低下が起きにくい反面、(あくまでも一般のバッテリーと比較しての話ですが)熱や過充電に弱いといわれています。例えば熱の影響を受けやすいエンジン周辺に熱保護カバーとともに装着されているケースが多いのもそのためです。一部国産車メーカーでは純正品はEFBの場合、AGMへの載せ替えは不適切であるという回答をしているものもあります。
現在の車はドライバーの方が想像している以上にコンピューターがしっかりと車両状態をモニタリングしてます。バッテリーもモニター対象の一つであるため、バッテリー交換後にバッテリー上がりの要因が車両側にいまだに残っている場合や車載コンピューターに交換のリセットやアダプテーションの必要がある場合もありますので、できれば速やかに車両の点検やテスターを使用した故障診断をおすすめします。