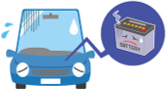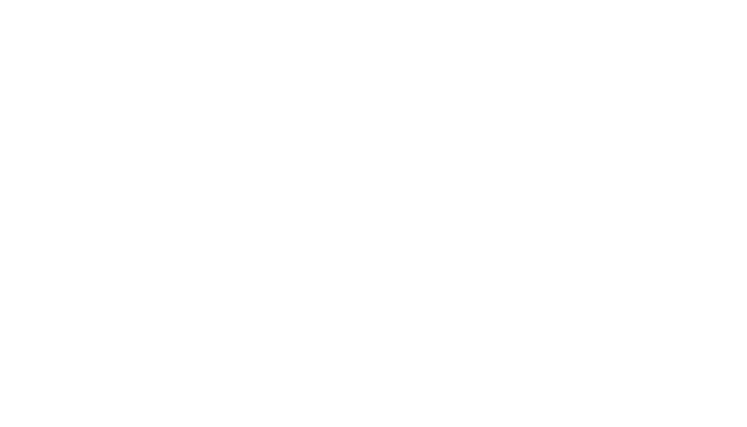 ”バッテリーの警告灯が灯いてます!!”
”バッテリーの警告灯が灯いてます!!”
バッテリー通信
2025年09月
警告灯とは 自動車のエンジンをかけるとすぐに”電球切れ”していないか確認するため一瞬点灯し、非常があると点灯する警告灯。特に平成29年2月以降は「審査時における車両状態」が規定され、「次に掲げるテルテールの識別表示が継続 […]
警告灯とは
自動車のエンジンをかけるとすぐに”電球切れ”していないか確認するため一瞬点灯し、非常があると点灯する警告灯。特に平成29年2月以降は「審査時における車両状態」が規定され、「次に掲げるテルテールの識別表示が継続して点灯又は点滅していない状態」でなければ車検を受けることができなくなりました。




バッテリー警告灯ではなく、充電警告灯

左記画像の警告灯の正規名称は正しくは「充電警告灯」です。一般的なドライバーには見た目からこの警告灯を「バッテリー警告灯」と呼ぶ方も多いので、ロードサービスのJAFなどではあえて「バッテリー警告灯」と表示しているようです。
しかしJAFにも警告灯が表示している原因について「発電機の故障やベルト切れによって点灯している可能性があります。そのまま走行を続けた場合、バッテリー電圧が低くなり、エンジンが停止します」と表記されており、バッテリーの不具合ではなく自動車の充電系統の異常を示す警告灯であることがご理解いただけると思います。
この警告灯が点灯した際の主な故障要因として、一例をおげるとオルタネーター本体の不具合やオルタネーターの駆動用ベルトの緩みなどの影響でオルタネーターが正常に作動せず、発電能力が低下し、バッテリーの充電率が規定以下になっても充電が進まず、結果としてバッテリー内の電気がなくなり、最終的にはエンストします。 この警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し、自動車の販売店など救援が必要となります。
また自動車はエンジンがかかっている間、何となくずっと充電していると思っている方も多いようですが、実際はエンジンがアイドリングや低回転のときは、オルタネーターの出力が低くなることがあります。また最近の車両ではエネルギー効率を高めるために、発電を制御するシステム(スマートチャージング)などが搭載されており、必要なときだけ発電し、逆に減速時やアクセルオフ時に回生ブレーキ等で発電しバッテリーを充電するなど車載コンピューターが統合的に制御しています。そのため普段車にあまり乗らない自動車ユーザーが、バッテリー上がるの予防のためとエンジンをかけるだけ、または長距離を走らないなどをするとかえってバッテリーの消耗を進めるなどの事象もよくあります。
警告灯が点灯しない?バッテリーの不具合
バッテリーの不具合が起こった時に必ず警告灯が点灯するわけではありません。たとえば代表的な事例は当然ですが寿命による”バッテリー上がり”がありますね。これ以外にも最近のクルマは車載コンピューターの性能が向上しモニタリンクしていますが、少し古いクルマでは指定の輸入車用のバッテリーでなく、国産車用のバッテリーに交換したがために容量不足で高速走行時にエアサスペンションが不具合をおこして”ロック”したこともありました。
一方近年では車載コンピューターへの依存度が高まる半面、まれに日本国内での自動車の使用条件が普段使いの市内走行に偏っているがために車両の状態とコンピューター制御のしきい値のアンバランスにより、警告灯が点灯するケースも見受けられます。これらは”故障”というよりは自動車メーカー側でプログラミングを見直し、「多少大目に」見てあげれば問題ない場合がほとんどですが、対策に数年要することもあり、その期間バッテリーを”無償交換”や”アップグレード”して対応しているケースもあるようです。
適度な走行利用、または補充電器によるメンテナンスがバッテリーの長期利用に繋がります。